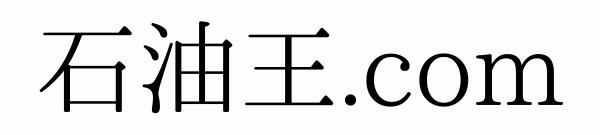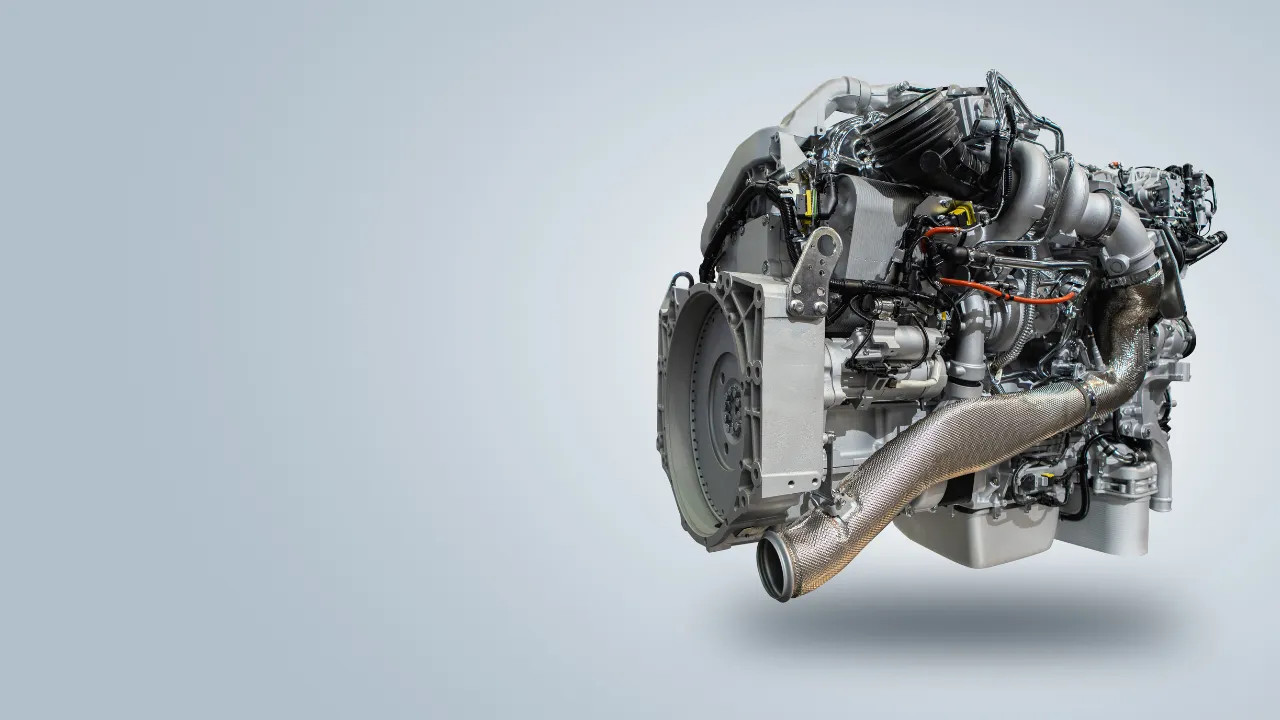ディーゼル車に使われる軽油は、ガソリンと比べて火がつきにくい燃料の1つ。
ライターであぶっても簡単には燃えず、引火点も高いのが特徴です。
しかし、ディーゼルエンジンでは、軽油を強力なエネルギー源として燃焼させ、力強いトルクを生み出しています。
本記事では、軽油が火がつきにくい燃料であるにもかかわらず、なぜエンジン内部ではしっかり燃えるのかを、燃料の性質からエンジン構造、燃焼プロセスまで整理して解説します。
軽油に火がつきにくい理由

まずは、軽油に火が付きにくい2つの理由を簡単に紹介します。
引火点が高い燃料だから
軽油の特徴としてまず挙げられるのが、引火点が高いということです。
ガソリンの引火点が約-40℃なのに対し、軽油は約40℃前後。
つまり軽油は、周囲の温度がある程度高くならないと蒸発せず、可燃ガスを作りにくいということです。
この性質によって、通常の状態では着火しづらい燃料となっています。
蒸発しにくく、気化しにくい
ガソリンは常温でも揮発性(物質が気体になりやすい性質)が高く、蒸発した気体に火を近づければ容易に燃え広がります。
一方、軽油は揮発性が低く、燃焼しやすい「気体」になりにくい点が特徴です。
ガスが充満した空間にライターなどの火種を付ければ爆発しますが、そもそも揮発しにくい物質のため、火が付きにくいとされています。
なぜ軽油はディーゼルエンジン内で燃えるのか?

軽油は火がつきにくいのに、ディーゼルエンジンでは確実に燃焼する。
ここには、ディーゼル方式ならではの「特殊な燃焼方法」が大きく関わっています。
ディーゼルエンジンは「圧縮着火」
1つめは、ディーゼルエンジンの燃焼方式は「圧縮着火」である点です。
そのため、ディーゼルエンジンならではの燃焼を起こせるのです。
圧縮比が非常に高い
ディーゼルエンジンでは、シリンダー内の空気をガソリンエンジンの約2倍近い圧縮比で圧縮しています。
高圧縮されることで、空気の温度は700〜900℃まで上がり、高い温度に達した空気と接触すると、火花がなくても自然に着火する。
ディーゼルエンジンは、軽油が燃えやすい環境をエンジン内部で強制的に作っているといえるのです。
高圧噴射装置が軽油を細かい霧状にする
ディーゼルインジェクターは、軽油を超高圧で霧状に噴射します。
霧化が進むほど空気との接触面が増え、燃焼しやすくなるため、高温・高圧の空気の中に細かな燃料ミストが入り込むことで、瞬時に自己着火が起こる仕組みです。
ディーゼルエンジンの燃焼4プロセス
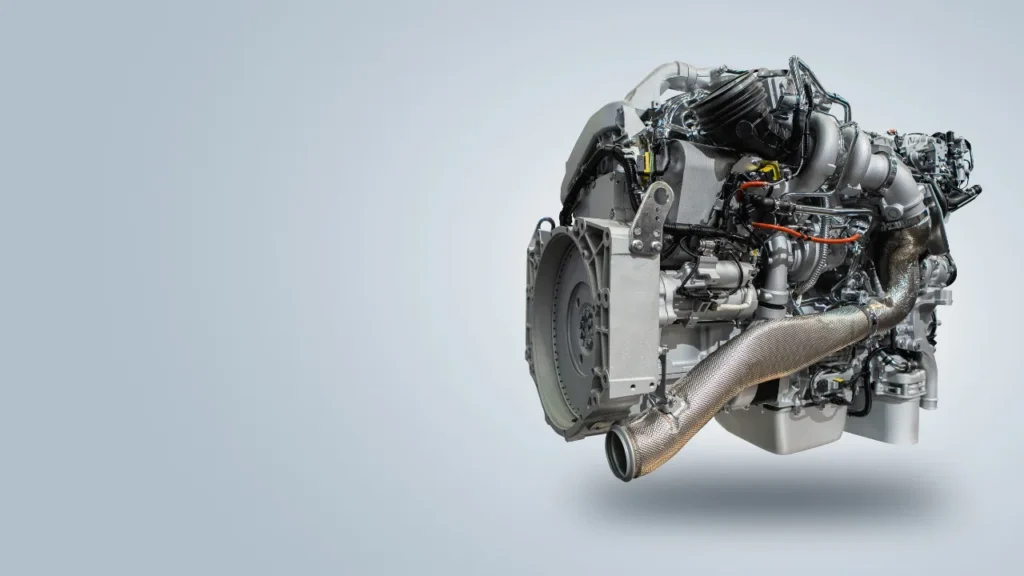
ここからは、エンジン内部で起きている燃焼の流れを順に追って紹介します。
ガソリンエンジンは空気と燃料を混ぜて吸い込むが、ディーゼルは空気のみ吸入する。この段階では燃料はまだ入らない。
ピストンが上昇し、シリンダー内の空気を一気に圧縮する。ディーゼルエンジンは圧縮比が高く、圧縮によって空気が高温に変化する。
圧縮上死点直前に、インジェクターが軽油を高圧で噴射する。霧化した燃料は、高温空気に触れた瞬間に自己着火する。
燃焼した混合気が膨張し、ピストンを押し下げる。これがディーゼル車特有の強いトルクを生む原動力となる。
軽油は火がつきにくい方がメリットがある

軽油は火がつきにくい性質を持つが、この特性こそがディーゼルエンジンに向いている理由でもあります。
不意な着火が起きにくい
ガソリンは揮発性が高いので、少しでも熱があれば蒸発して炎が広がりやすい一方で、軽油は安定した燃料のため、燃料タンク内や配管内で勝手に気化して、爆発的に燃えるような危険性が低いです。
そのため、突然の着火などの事故が起こりにくいため、ディーゼルエンジンに向いています。
圧縮に耐えられる
圧縮比が高いディーゼルエンジンでは、燃料が勝手に気化してしまうと点火のタイミングが安定しません。
しかし、引火点の高い軽油であれば、意図したタイミングでのみ着火させられるため、安定した燃焼制御が可能です。
ディーゼルエンジンは軽油の“特性を利用した”仕組み

軽油は火がつきにくいものの、ディーゼルエンジンはその逆の性質をうまく利用しているといえるでしょう。
この特性があるからこそ、シリンダー内部で完全にコントロールしながら燃焼させることが可能なのです。
まとめ

軽油は引火点が高く蒸発しにくいため、通常の環境では燃えにくい燃料です。
こうした仕組みによって、火がつきにくい軽油でも確実に燃焼させることが可能です。
また、軽油の特性は、むしろディーゼル方式の燃焼制御に適しており、その結果として高いトルクと効率的な燃焼を実現するエンジンが成立しているといえるでしょう。
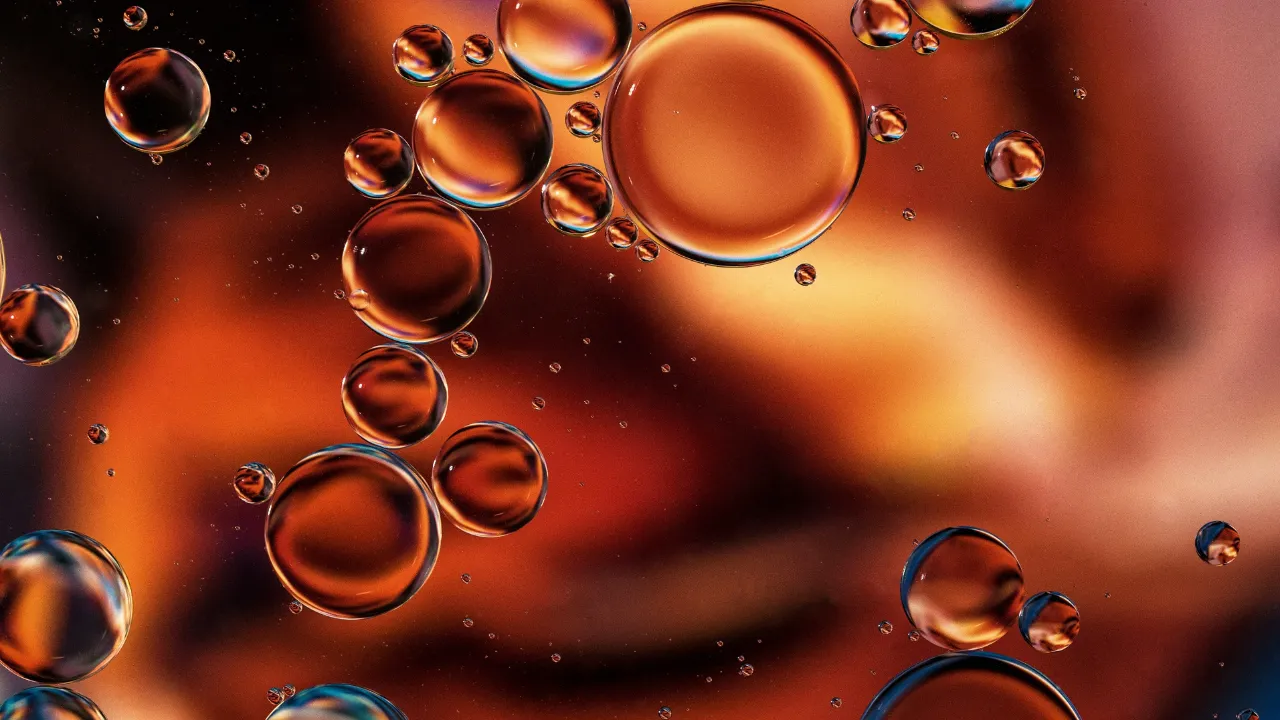



.webp)


.jpg)